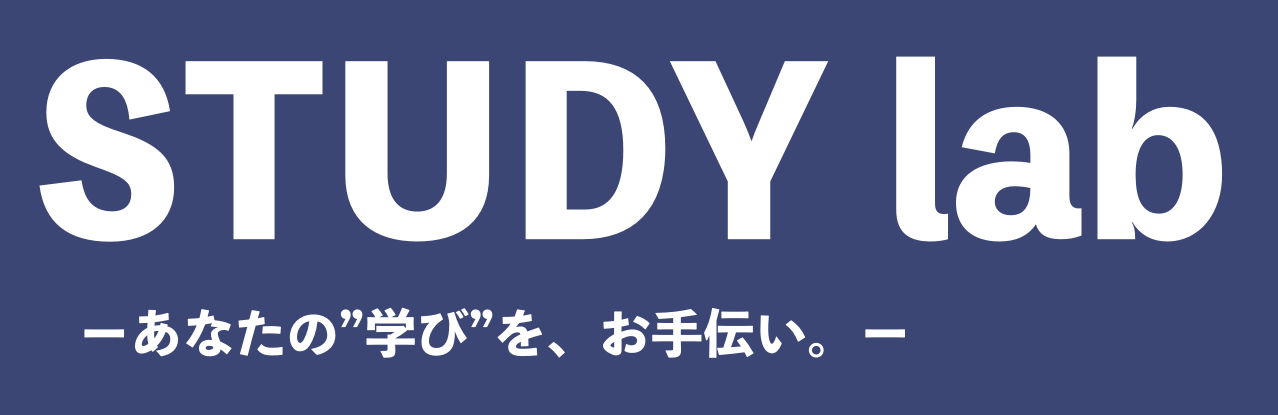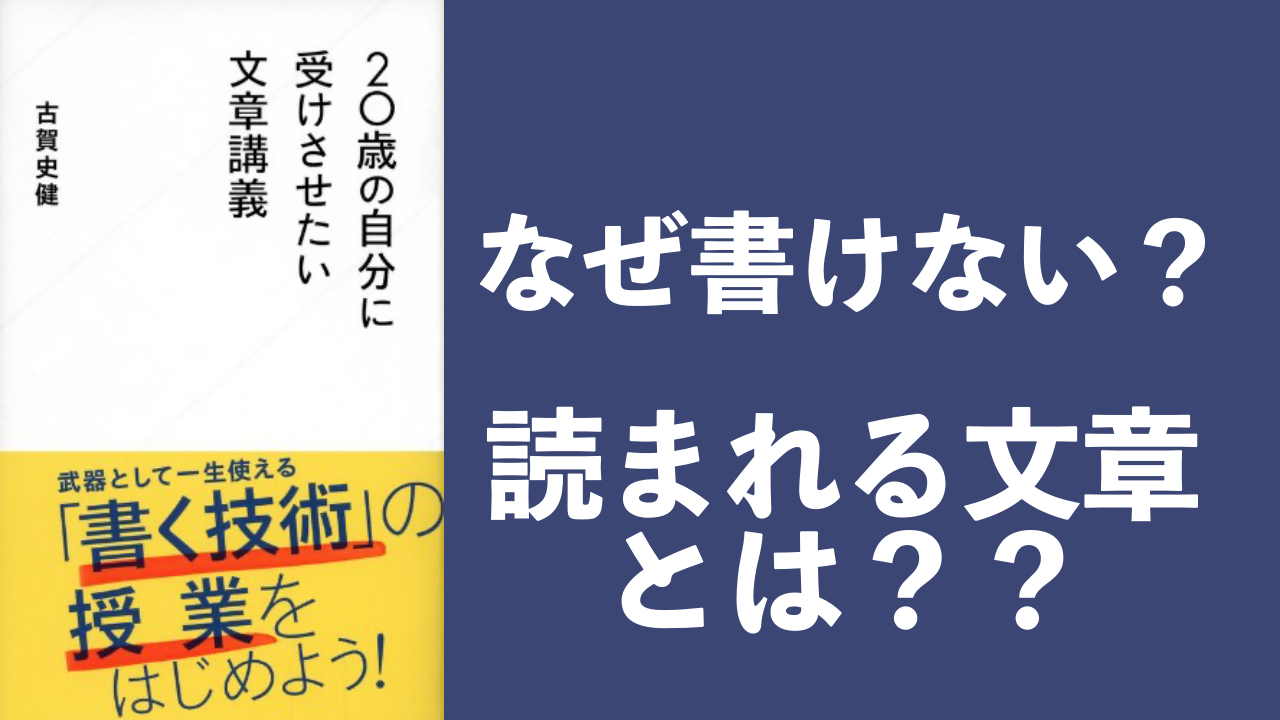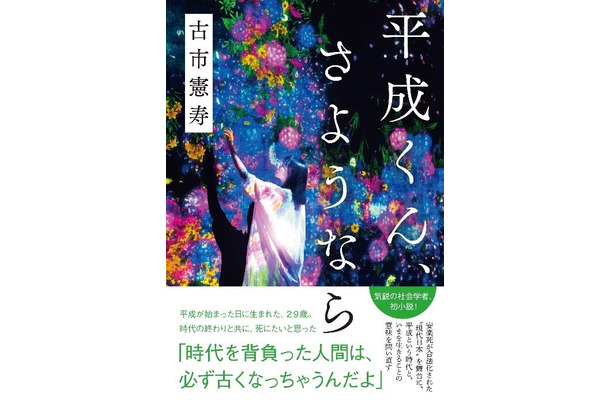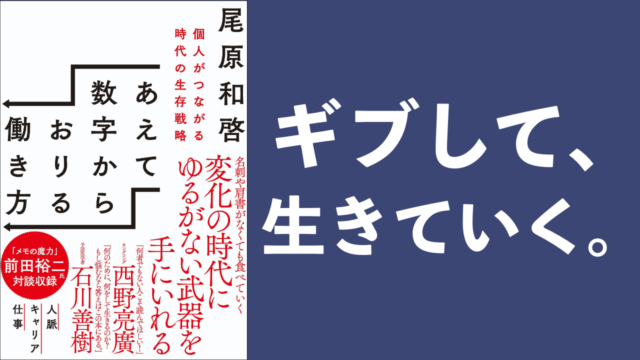こんにちは、もりもと (@MorimotoKoki)です!
この記事では、古賀 史健さんの著書『20歳の自分に受けさせたい文章講義』の要約をしていきます。
こんな思いが少しでもある方は、ぜひ目を通してみてください!!
この記事の内容は以下の通りです。
- 頭のぐるぐるを解消し、考えを「翻訳」できれば文章は書ける
- 「書く=考える」で、「翻訳」に近く
- 文章を書くときは、読者と同じ椅子に座ることを意識する
本記事の信頼性
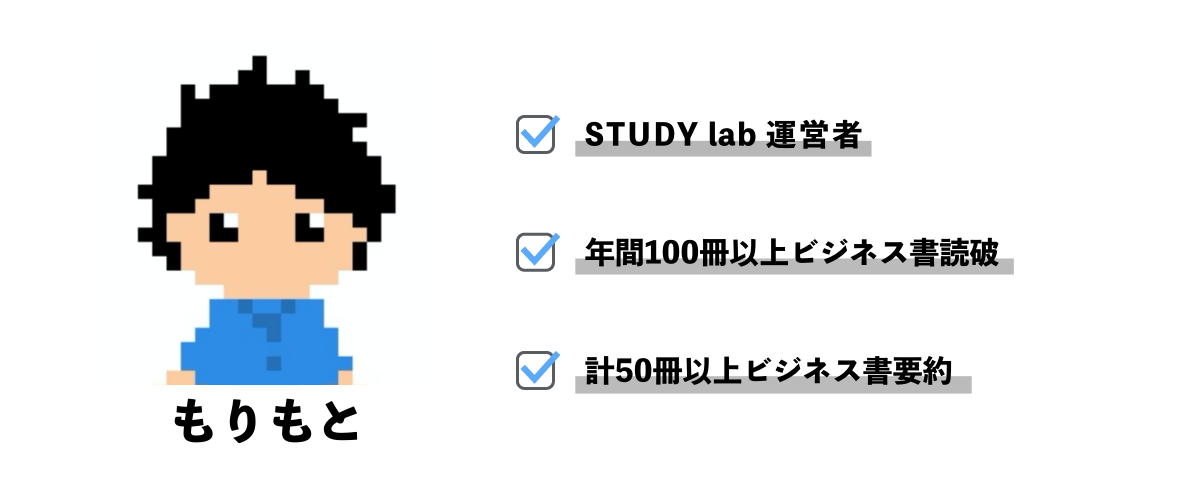
3分で読めます、この本の内容を把握したい方は、最後まで読んでみてください
なぜ書けないのか
文章をうまく書けない人は、なんでうまく書けないのでしょう??
それは、、、
頭の中が、ぐるぐるしていて、考えを文章に「翻訳」できないから
なぜ翻訳できていないのか説明して行きます。
文章をうまく書けないという人でも、話して説明することは大半の人ができます。
話すことはできるのに、書くことはできない。
その理由は、
会話では、表情,身振り,声の抑揚など、意思疎通の手段がとても多くあるのに、「文章は視覚のみしか使うことができないから」です。
最高の縛りプレイです。
なので、最初は書けないなんて当たり前なんです。
今からでも全然遅くはないので、ここから文章の書き方を要約して行きます。
書く技術=考える技術
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、書く技術を学ぶだけの本ではありません。
この本で古賀さんは、「書く技術=考える技術」としています。
なぜか??
書いていくうちに、視覚的理解が可能になり、自分の理解がどんどん深まるからです。
我々はよく、わかったこと書こうという考えになりがちですが、それが間違いなんです。
書くことで、わかるようになるんです。つまり、書くことは考えること。
そして、考えた先に得られる本当の理解を用いることで、自分の頭の中にある考えを「翻訳」することができ、”良い文章”をかけるようになるんです。
では次から、実際に文章を書く際に気をつけること、テクニックを紹介して行きます!
文章のリズムに気をつける

良い文章=良いリズム
良い文章の何が良いのか、、、リズムです。
そしてリズムとは、「論理展開」です。
では、論理展開をスムーズに行う方法を説明して行きます!
接続詞を使え
接続詞(例:なので,よって)は、文と文をつなぐ役割を持っています。
なので、接続詞を使いこなせれば論理展開もスムーズになるんです。
では接続詞、どう使えばいいのか??
たっっくさん使いましょう。
文章をうまく書けない人は、接続詞をそもそも全然使っていません。
なので、接続詞を使うことを意識していくことで自然と、論理展開をスムーズにしていくことができます。
文は目で読む
我々が文を読むとき、読む前に「見る」という行為を挟みます。
なので、視覚的なリズムが悪いと、そもそも読む気を奪ってしまう結果になります。
視覚的リズムを向上させる方法は、3つあります。
1.句読点を、一行に一つは入れる。
2.改行は、五行に一回は行う。
3.漢字と仮名のバランスを整えるために、漢字はキーワードくらいに考える。
以上の3つです。
これらに気をつけて、視覚的リズムを向上させましょう!!
文章の構成
主張→理由→事実の連動
文章を書く上で、「主張→理由→事実」の連動は必須です。
・主張(結局何が言いたいのか)をはっきりさせる
・理由は、できるだけ数字などを使って細かくする
・例となる事実で、説得力をUP
文章の構成は、これらを気をつけるだけで十分です。
人に読まれるための意識
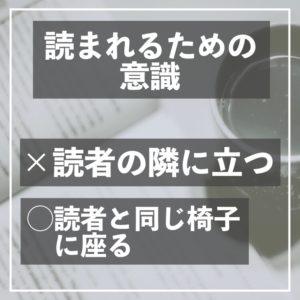
文章は人に読まれないと意味がない
どんなに良い内容でも、人に読まれなければ文章を読まれなければ悲しいですよね、
なのでここでは、「いかに書いた文章を読んでもらうか」という点に関してテクニックを紹介して行きます。
読者と同じ椅子に座る
文章を書くときは、読者と同じ椅子に座る勢いで、読者の気持ちを考えましょう。
この記事でも述べていますが、相手側の立場に立つことは本当に大切です。
なぜなら、”翻訳”のための理解が深まるから。
まとめ
この記事では、僕が本当に大事だと思った点を、抜粋してようやくしているので、
もっと詳しく知りたい人は、ポチることをお勧めします!
電子書籍プレゼント
フォロワーの方々や、身内の人たちに、「本の読み方」を相談されることが増えてきました。
ありがとうございます!!
そこで、『正しい本の読み方』と言う電子書籍を作成しました!!
以下の公式ラインに登録して、スタンプを送っていただくだけで、無料でお渡しするので、是非ご登録ください!!