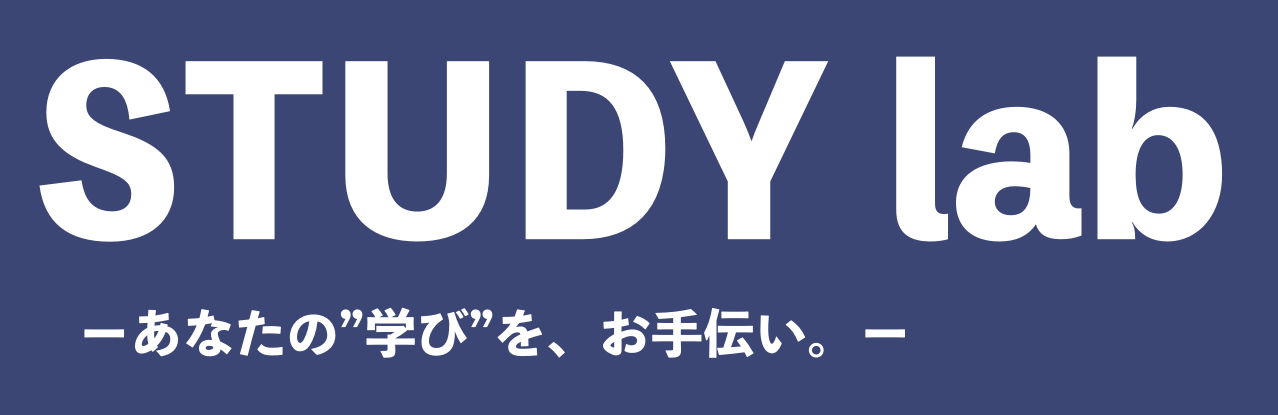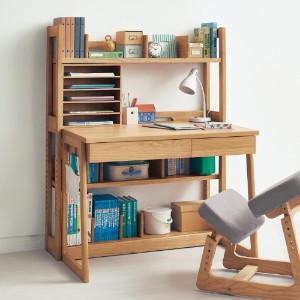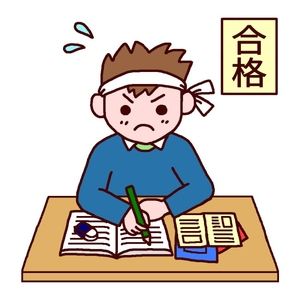こんにちは、ハカセです!
今回は、僕がずっと気になっていた本である『東大読書』を読んだので、
この本から学んだことを、書評という形で紹介しようと思います!
この本です!
『東大読書』の著者はどんな人なのか?
西岡壱誠(にしおか いっせい)
東京大学3年生。歴代東大合格者ゼロの無名校のビリ(元偏差値35)だったが、東大受験を決意。会えなく2浪が決まった崖っぷちの状況で「『読む力』と『地頭力』を身につける読み方」を実践した結果、みるみる成績が向上し、東大模試全国4位を獲得。東大にも無事合格。
(著書内、著者紹介より引用)
簡単に言うと、元々は勉強ができなかったが、本の読み方を変えることで、
劇的に成績を上げることに成功した東大生ということですね。
『東大読書』の内容と主張
「本の読み方」を変えるだけで「地頭力」は鍛えられると主張する著者が、5つのSTEPに分けて、読書法を紹介しています。さらに、読む本の選び方も紹介されています。
今回は、読書法に関しての内容に絞ろうと思います。
まず前提ですが、この本は、
STEP1 「読み込む力」を劇的に上げる・・・・・・仮説作り
STEP2 「論理の流れ」がクリアに見える・・・・・取材読み
STEP3 「一言で説明する力」を鍛える・・・・・・整理読み
STEP4 「多面的なモノの見方」を身につける・・・検証読み
STEP5 「ずっと覚えている」ことができる・・・・議論読み
の5STEPで構成されています。
ハカセの感想
僕と、著者の方の考え方に共通点が多いこともあり、かなり良い本だと感じました。
初めから、マーカーが引いてあり、読む側のことも考えられており、とても読みやすかったです。
共感する点や、とても学べる点がいくつかあったのですが、
その中でも、僕がこれは、自分も伝えたい!と思うことについて、掘り下げてみようと思います。
僕のこのブログは、「勉強法ハカセ」なので、読書法を勉強法と捉えてお話しします!
「アウトプット」で全てが変わる
超共感。
この一言に尽きます。
著書内では、STEP5の中でアウトプット法を紹介しており、その中で著者は、
「アウトプットをすることを意識してインプットをする」ことの大切さを語っています。
娯楽として読書をしている方には関係ありませんが、この記事を読んでいる人は、
何かしら勉強のために本や参考書を読んでいると思います。
そんなあなた、何も考えずにぼーっと本を読んでいませんか?
読めば知識になり、勉強になっていると思っている人はとても多いです。
受験生時代の僕もそんな時期がありました。
参考書を1周しては、次の参考書。
参考書に書いてある「情報」を自分の「知識」に変えなければいけないのに、当時の僕は、何も考えず、ただ量をこなしていました。
そうです、当時の僕は、アウトプットのことを何も考えていなかったのです。
インプットをするときに、アウトプットのことを考えるだけでいいんです!
その一工夫で、効率が何倍にもなってきます。
アウトプットの仕方
最後に、アウトプットの仕方を紹介します。
著者は著作内で、感想でも良い。と話しています。
僕もそう思います。
アウトプットと聞いて、かしこまらなくてもいいんですよ、
ただ、本を読んだら感想を友人に話してみるとか、
受験生であれば、模試が終わってそのままにするのではなく、あそこは難しかったなー。なんて友人と話すだけでも変わってきます。
まずは、実践してみることが大事です!
〜まとめ〜
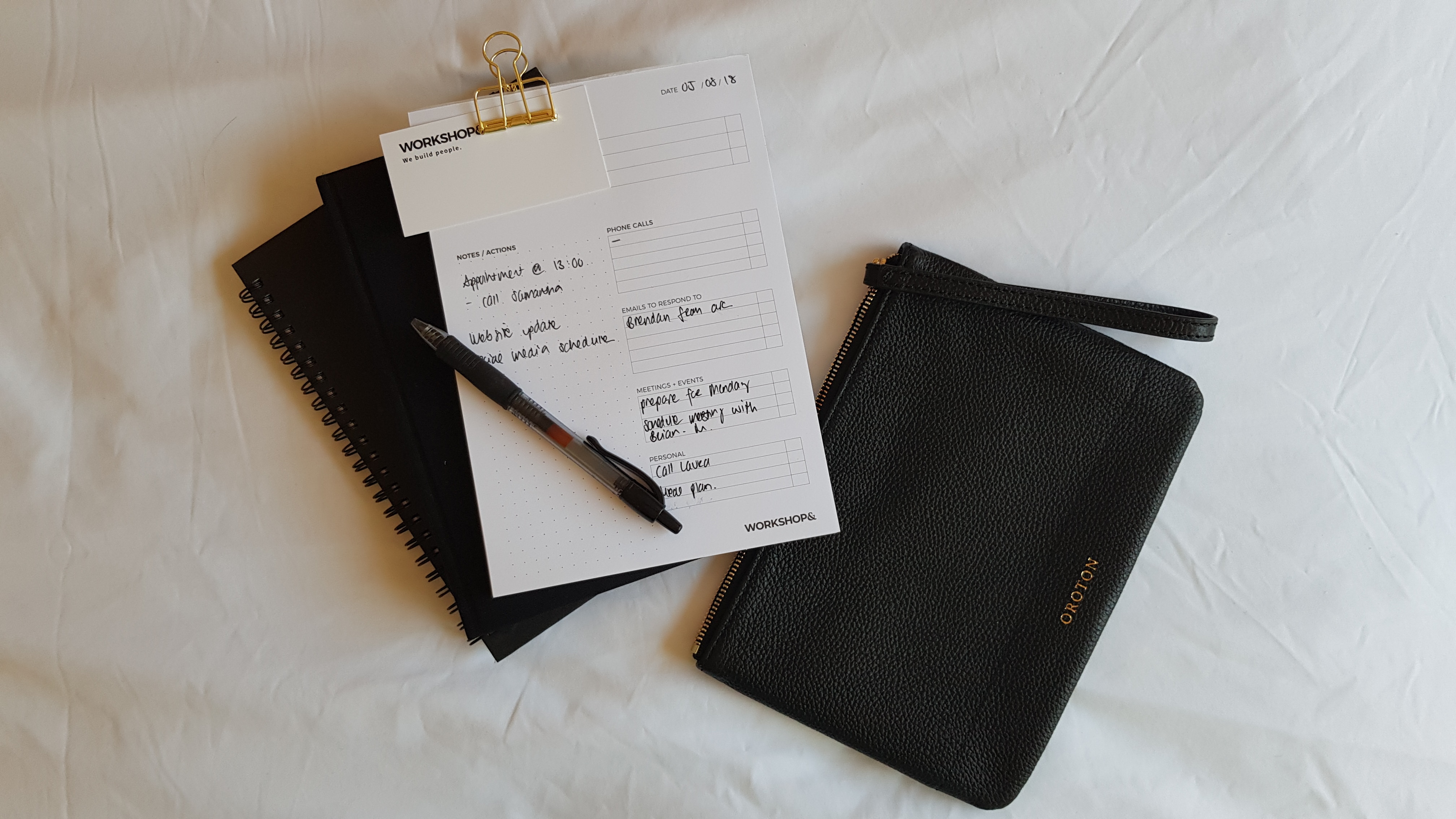
『東大読書』、学べることが多く、何度も読もうと思える1冊でした。
本を読むことで勉強をしている人にとっては、読まない手は無い!と言える内容です!
リンクを貼っておくので、是非、買って読んで見てください。
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書 [ 西岡 壱誠 ]
今回は以上でーす^^